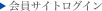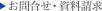人材育成コラム
“人財”育成のツボ
2018/12/20 (連載 第115回)
平成最後の年の暮れに……
ITスキル研究フォーラム 人財育成コンサルタント / PSマネジメントコンサルティング 代表
安藤 良治
一世代前の年号は平成といわれ31年、そして今の年号もほぼ同じ年数を過ごしてきた。
ここで現年号の30年を振り返りたい。
現在の年号の始まりとともに日本では2020年に東京でオリンピックが開催され、その5年後には大阪で万博が開催された。
それなりのにぎわいはあったものの、1964年の東京オリンピック、1970年の大阪万博ほどには日本経済へのインパクトはなかった。
むしろ、誘致の際にバラ色に描いていた皮算用は、大幅な支出増により、その経済的な負担の責任を問う世論でしばらくもめていた。
当時は、そのこと以上に深刻だったのが、人手不足の問題だった。人が集まらないために工期が延びたり、一部の企業では建設途中で倒産したりするといった事態も起きていた。
政府は、人手不足問題に対応するために、慌てて技能実習制度という何とも中途半端な制度を設けて、外国人を働き手として門戸を開いたものの、日本の身勝手な制度に対象国から見放される事態となってしまった。
その頃、日本では労働法というのがベースになっていて、働く人=労働者として「働いた時間」と「働いた場所」を念頭に置いた法律の下で様々な規制があった。今では、働く人を労働者といっていた時代があったのは信じられない人も多いだろう。
日本の雇用に関する歴史をたどれば、かつては終身雇用、年功序列、企業別組合という3つの特徴を持ち、第2次大戦後の戦後復興を奇跡的に成し遂げた国として、世界的にも注目される時代もあったようである。
この時代には、企業と働き手が運命共同体として、一つの企業に献身的に働くことが常識だった。献身的に働く人を保護する目的で制定されていたのが労働法である。
ところが時代は変わり、2020年のオリンピックの頃には、献身的に働くことよりも「働き方改革」というフレーズで、まるで働かないことを美徳とするような機運が起きていた。いつの間にか、日本の生産性は先進国のなかでも著しく低い国として評価され、日本生産性本部が2017年に発表した「労働生産性の国際比較」によれば、当時の先進7カ国のなかで1970年代以降最下位の状態が続いているとある。働くことのモチベーションが大変低い状況に陥っていた。
当時の働き方改革は、とにかく負のサイクルを助長するような取り組みが多かった。とりわけ、労働法の根本を見直すことなく、一つの企業で働くだけでなく、副業という他の企業でも働いても良いとする制度が政府の主導で導入され、労働法との矛盾に、混乱に拍車をかけたことは想像に難くない。
2025年の大阪万博がその混乱の最も高かった頃ではなかろうか。
でもその混乱が問題の根本原因にメスを入れることになったのだから何が幸いとなるかは分からないものである。
1945年に制定された労働法が全面的に見直され、新しく「雇用契約法」として制定されたのが2030年。導入当初は様々な問題が指摘され度々改正がなされてきたが、これが現在の企業と働く人との契約のベースとなった。
かつての日本における雇用の特徴とは決別し、企業の責任と同時に働く人の自己責任を明記した法律が、働く人の主体的な行動を導き出した。
かつては「定年」という概念があったようである。60歳とか65歳で強制的に辞めなければならない労働契約が日本には存在した。その代わり日本では企業側が雇用契約を打ち切る解雇は特別な事情がなければできないとすることで「終身雇用」という特徴を生み出していた。
今では「年齢で打ち切るなんて信じられない!」と皆思うであろう。その時代のその国の事情により、常識というものは変化することの一つの表れであろう。
90歳でも現役で働いている人はたくさんいるのに、当時は60代で現役を引退しなければならなかった。一部の人は、その後も自分の専門性を生かして個人事業 主として活躍する人、NPO法人などでボランティアにいそしむ人、あるいは健康増進のためウォーキング、家庭菜園でのちょっとした農作業にいそしむ人などもいたが、多くは早い時期から介護のお世話になり、ただでさえ人手不足のなかにあって、介護職の人手不足は深刻な問題だった。
突然、やることがなくなり、途方に暮れる。こんなことになったら、老いが早まるのは自明といえる状態だったのであろう。終身雇用という名のぬるま湯の雇用制度が、弱い日本を形成していたといえよう。
さて、雇用契約法のベースは、働き手の自己責任を明確にしていることである。
企業との雇用契約は、基本的には請負型となり、仕事の案件ごとに契約を交わすことが主流となった。従って、一つの企業に束縛されることなく、自分の専門性を発揮して、複数の企業と契約することが常識となった。一方でそういう契約にたどりつけるよう自分の専門性を磨く努力は、20代の人も70代の人も同じ土壌で競い合うようになった。
企業においては、プロジェクト型の仕事が中心となり、一つのプロジェクトが発足するとプロジェクトマネジャーが任命され、そのプロジェクトに真に必要なメンバーだけが必要な期間契約して参加するというチーム編成がなされることになった。IT業界においてもプロジェクトマネジャー以上に注目されているのが、プロジェクトのシナリオを描ける「プロデューサー」である。
プロデューサーの腕次第でそのプロジェクトに必要な専門性を持った人材を集めることができ、素晴らしいプロジェクトチームを編成することができるようになった。
プロジェクトマネジャーが担当するプロジェクトに集中できるようになったのも日本の生産性を向上させることにつながった。
かつては、企業の中に人を抱え、いろんな部門に分かれて人を配置していた。
プロジェクトマネジャーは、自分のプロジェクトに集中することよりも抱えている人材の仕事の確保にも奔走し、自分の成果は一つのプロジェクトの損益よりも部門の業績が優先されるという何だか不透明なマネジメントを強いられていた。
優秀な人は30代の前半から、プロデューサー、プロジェクトマネジャー、プロジェクトリーダーに就き、チームの中には80代のエキスパートを加えることも珍しくなくなった。
かつての企業では、課長、部長、本部長と昇進することが一つのステータスとなっており、一度組織の高い地位に就くと、社会的な体裁なのかプロジェクトの一メンバーとして参加することは難しかった。このタテ型の組織構造も日本の生産性を低いものにしていたといえよう。
古い時代をタテ社会と呼ぶならば、雇用契約法が成立した2030年がヨコ社会に移行した原点といえるのではなかろうか。老若男女が良い意味で競い合い、また外国人もそこに同じように参加して働ける環境ができたことが、日本を元気にさせた転換点といえる。
そうそう、2050年の日本の誇る技術は、ロボット、都市部の整備された交通ルールによる自動運転車、そして原発の廃炉技術である。
深刻だった人手不足の多くは、ロボットの発達と浸透により、介護の世界で大活躍し、現在では多くの家庭でロボットが購入され、家事、介護、そして話し相手として活躍している。
そういえば、米国の未来学者レイ・カーツワイルが2005年に「シンギュラリティ」を提唱し、2045年には人工知能が人類の知能を超える転換点となると予測したが、今のところ人とロボットはうまく付き合っているように見える。
日本における自動運転車の進展は、2025年の大阪万博がきっかけとなった。この万博で自動運転車専用エリアを設けたことが、渋滞も事故もない交通機関として認知され、続いて首都高速を自動運転車の専用道路として規制したことも自動運転車の浸透に一役買ったようである。
今では、原発は世界的にノーとなったが、ここに来るまでは幾度も論争が起きた。
日本は、震災により福島原発で大変悲しい事故を起こしてしまったにも関わらず「廃炉」を決断するまでには、何度政権の交代があったことであろう。
代替技術が不確かだっただけに決断ができなかったようである。時代は、技術の進展とともに負の遺産を整理することに成功してきた。
かつては「奇跡の鉱物」としてもてはやされたアスベストは、肺がんや中皮腫の誘因となるとして追放され、グラスウール(ファイバーグラス)やセラミックファイバーに代替された。
フロンガスは、空調や冷蔵庫に欠かせないものとして普及していたがオゾン層を破壊して温暖化の原因となっているとして、代替フロンに置き換えられた。
プラスチックも海洋汚染につながるとして、議論されている。
原発は、負の遺産となる。多くの人がそう思いながらも廃炉への決断の道のりは長かった。ようやく、その道筋が見え、日本が廃炉技術で世界に一歩リードできている点は喜ばしいことであろう……。
さて、平成の30年も多くのことが起こりました。平成として年の暮れを迎えるこの時期に2050年という時期を設定して新しい年号の30年を振り返る、という勝手な想像をしながら描いてみました。
どんな世界が待ち受けているのか?それは、私たちが知恵を出し、努力することでどんな形にも変化します。
一人ひとりが夢を持ち、生活することが楽しいと思えるような社会であって欲しいと願っています。
読者の皆さま、今年もお読みいただいてありがとうございました。
皆さまにとって、2019年が幸多き年となりますようお祈り申し上げます。