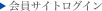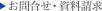人材育成コラム
“人財”育成のツボ
2019/03/20 (連載 第118回)
社員のやる気を引き出すアメーバ経営
ITスキル研究フォーラム 人財育成コンサルタント / PSマネジメントコンサルティング 代表
安藤 良治
2000年代の初頭に起こったITバブル崩壊の時期、現場のあちこちで聞こえていた声です。
ITバブルに乗って、採用は毎年500人を超え、協力会社の人まで入れると毎年ビルを1棟新しく借り上げるほどの勢いで拡大していったそれまでの数年間がうそのように、拡大路線からの転換を余儀なくされた時期です。
親会社からの注文は減少し、協力会社への発注は減っていきます。
当時の経営トップは、社員の人員削減は行わず、構造改革で乗り切るとの方針を打ち出し、人員管理を担当していた私が事務局となって推進することになりました。
まず行ったのが、原価構造の分析です。
人員構成は、管理部門と営業部門合わせて15%程度、直接部門となる設計開発部門が残りの85%でした。親会社からの注文が減っている以上、外販に販路を拡大する必要があるため、営業部門は強化する必要があります。必然的に管理部門の人員をどれだけ削減できるかが、一つの課題になりました。
しかしながら、全社の7%程度の管理部門だけにメスを入れても、全体の効果はさほど高くありません。
そこで、直接部門である設計開発部門の構造にもメスを入れる必要がありました。当時の間接員の定義は、課長以上は管理業務を行うので間接員とする。また、営業と連携して受注活動を行うSEをプレSEとして間接員とする。という定義の下、人員管理・予算を組んでいたので直接部門の中でも15%が間接員となっていました。営業管理部門と合わせて3割が間接員、つまり見積単価を計算する上でのベースとなる直接員は全社の7割の人員でした。
次に直接員の直接業務比率に着目すると、各部門で設定することができるもののそれまでの慣例から、どの部門もおおむね80%を直接業務とする設定がなされていました。
7 (直接員比率) × 8 (直接業務比率) = 56
全社員が直接業務に従事している時間は、なんと全体の56%でしかなかったのです。しかも、間接業務扱いとなっている対象の多くが管理職以上ですから、人件費まで考慮すればもっと間接費の比率が高くなる計算です。
これでは、見積単価が高くなるのは当たり前といえます。
それでもバブル期は、注文が多く、多くの協力会社の人たちが従事してくれたおかげで全体の直接業務のバランスが保たれていたのです。協力会社への発注が減ったとたんに露呈した問題点でした。
そこで、この比率を何とか改善しようと
8 (直接員比率) × 9 (直接業務比率) = 72
を打ち出して、全社の構造改革を推進しました。
具体的には、管理部門従事者の営業・設計部門へのシフト、直接業務に従事する課長層の直接員化、プレSE活動は、プレSEという人を固定するのでなく、誰でもプレSE活動に従事できるよう作業コードとして設定し、予算化する仕掛けに改訂しました。
当時の活動を振り返ると、大変だったのは管理部門の人員削減です。幹部の強い意志と人事部は率先して3分の1の人員をシフトすることで働きかけました。現場を回ると周囲の関心は、事務局として管理部門の人員削減を達成できるかに集中していたように思います。
管理部門の人員削減と並行して、現場を回り部門長に見積単価を下げるための構造改革の提案を行いました。すると、「見積単価が下がるんなら、いいんじゃない」と特段の反対意見もないまま 「8×9=72」 の改訂の賛同をいただくことができました。
個別に各部門を回り了承を取り付け、経理の管掌役員の賛同を得たところで、経理提案の案件として役員会の承認を得て、上記の改革が実現しました。
この改訂により、以下の3つのことが達成できました。
(1)見積単価の2割弱の引き下げ
(2)優秀層の積極的な課長登用(従来は間接員となるため抑制傾向にあった)
(3)誰でもプレSE活動ができることによる外販受注活動の活性化
ITバブル崩壊後の厳しいこの時期を経験したことで、人事部門は、経営をサポートしながら、「社員が元気になる」ための諸施策をどんどん提案していけば良い、そういう役割を担っているとの思いが強くなりました。
諸施策の提案はどこが行うのが筋か、を考えなくては、「実」をとることができません。上記の改革案は、私が現場の部門長の意見を添えて経理の管掌役員に説明、了承を得た段階で、今度は経理管掌役員が社長の承認を得るための資料、つまり経理起案の資料作成にも協力しました。そして、社長の承認を得るや、人事管掌役員に経理の動きとして報告しました。
正攻法とはいえない動きだったかと思いますが、今でいうステークホルダマネジメント的には、「実」をとることができる唯一の動きだったと思っています。
この時期、よく読んでいたのが、稲盛さんの本で、京セラのアメーバ経営に強い関心を寄せていました。
「当社でもアメーバ経営を学んで導入したい」と思いました。
しかしながら、その時期にはアメーバの概念程度しか表に出ておらず、社内に有力な賛同者も得られないまま、やがて私は独立して社を後にしました。
2017年9月待望のアメーバ経営を具体的に解説した書が発行されました。
「稲盛和夫の実践アメーバ経営」(稲盛和夫著、日本経済新聞社刊)
「まえがき」部分を引用させていただきます。
アメーバ経営では、会社を小さな組織に分け、それぞれを「アメーバ」と呼ぶ独立採算部門にしていく。ひとつひとつのアメーバは「売上最大、経費最小」という経営の原理原則を全員で実践する。リーダーは自分のアメーバの目標をメンバーと一緒に立て、その達成を目指す。メンバーも、それぞれの持ち場、立場で目標達成に向けて努力し、個人の能力を最大限に発揮していく。
その結果、社員は仕事を通じて自身の成長を実感し、目標を仲間と共に達成する喜びを味わう。このような全員参加経営によって、経営理念の「全従業員の物心両面の幸福」を追求していくのである。
アメーバ経営によって京セラは、創業以来一度も赤字になることなく発展を続けている。同じく私が創業し、アメーバ経営を導入した第二電電(現KDDI)や、私が再建に携わりアメーバ経営を導入した日本航空も高収益を維持している。
当初、アメーバ経営は京セラ独自の経営ノウハウであり、門外不出にすべきだと考えていたが、多くの方々に知ってもらい、活用してもらうことが社会の発展に役立つと考え、2006年に「アメーバ経営」(日本経済新聞社)という書籍を出版させていただいた。おかげさまで同書は好評を博し、現在も多くの方に読み継がれている。
一方でもう少しくわしいアメーバ経営の解説書がほしいという声もいただくようになった。また、冒頭にも述べたように、日本経済低迷の要因のひとつが社員ひとりひとりの思いや能力を十分に生かせていないことにあると考えていたので、アメーバ経営の価値をさらに多くの方々に理解してもらうことは意義のあることだと考えるようになった。
そこで本書が発刊されたということです。その結果、社員は仕事を通じて自身の成長を実感し、目標を仲間と共に達成する喜びを味わう。このような全員参加経営によって、経営理念の「全従業員の物心両面の幸福」を追求していくのである。
アメーバ経営によって京セラは、創業以来一度も赤字になることなく発展を続けている。同じく私が創業し、アメーバ経営を導入した第二電電(現KDDI)や、私が再建に携わりアメーバ経営を導入した日本航空も高収益を維持している。
当初、アメーバ経営は京セラ独自の経営ノウハウであり、門外不出にすべきだと考えていたが、多くの方々に知ってもらい、活用してもらうことが社会の発展に役立つと考え、2006年に「アメーバ経営」(日本経済新聞社)という書籍を出版させていただいた。おかげさまで同書は好評を博し、現在も多くの方に読み継がれている。
一方でもう少しくわしいアメーバ経営の解説書がほしいという声もいただくようになった。また、冒頭にも述べたように、日本経済低迷の要因のひとつが社員ひとりひとりの思いや能力を十分に生かせていないことにあると考えていたので、アメーバ経営の価値をさらに多くの方々に理解してもらうことは意義のあることだと考えるようになった。
社員の活力を引き出し、元気な会社にしたいという思いのある方にはぜひお勧めしたい著書です。
管理会計は、その時期、その置かれた環境に合わせて適時改訂していくものです。会社を元気にする原動力となり、結果として社員のやる気を引き出すことにつながります。
アメーバ経営は、きっと現時点で課題となっている事柄の解決につながる要素を持ち合わせていることでしょう。
実は、「アメーバ経営」と本コラムで取り上げてきた「ティール組織」、相通じるものがあります。学び、実践に展開してみてはいかがでしょうか。