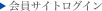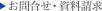人材育成コラム
“人財”育成のツボ
2018/4/20 (連載 第107回)
この仕事から期待すべきものは何か?
ITスキル研究フォーラム 人財育成コンサルタント / PSマネジメントコンサルティング 代表
安藤 良治
その多くが、「残業縮減」「休暇の増加」など、働く時間を減らすことに注目しているように思います。
グローバル競争の中で厳しい状況に立たされている日本の経営環境からすると、業績改善のためのさらなる取り組みをしなければならない課題が多くあるのに、働かないことを美徳とするような記事が増えることに違和感というか、ある種の危機感を持っていました。
そんな折、日経ビジネスNo.1935 4月2日号で「真の働き方改革」というテーマで日本電算の取り組みが紹介されていました。
今回の日本電産の取り組みを紹介した特集は、「なるほど」と共感できる取り組み事例です。その一部を紹介しますが、ぜひ本文(有料記事です)をご覧ください。
2018年長者番付6位の日本電産永守社長は、「元旦以外、仕事は休まない」と公言し自他共に認めるハードワーカーでした。その永守社長が、「今年は45年ぶりに正月三が日、一度も会社に来なかったよ」と変身しました。
会社は「2020年度までに残業ゼロ実現」を掲げ、働き方改革の旗を振っています。
と、ここまではほかの例と同じように「働く時間の削減」を目標として取り組んでいる紹介ですが、目的は「20年度までに生産性を倍増」することであり、徹底した構造改革で生産性を2倍に引き上げ、グローバル競争を勝ち抜くという筋書きです。生産性が向上した結果として、「残業ゼロ」を実現する。
会社を挙げて、無駄な仕事を抽出し、改善する。その実現のために1,000億円を投資する。
日経ビジネスのテーマが「真の働き方改革」とあえて「真の」と付けて日本電産の取り組みを紹介しているその本気度が伝わってきました。
「働き方改革」に取り組まなければならない背景の一つ(最も重要と私が思う課題)に日本の労働生産性の低さがあります。
日本生産性本部が2017年12月に発表した「労働生産性の国際比較」によれば、
日本の労働生産性は、米国(69.6ドル)の3分の2程度の水準で、ニュージーランド(42.9ドル)をやや上回るものの、英国(52.7ドル)やカナダ(50.8ドル)をやや下回るあたりに位置している。主要先進7カ国でみると、データが取得可能な1970年以降、最下位の状況が続いている。
とあります。
■日本生産性本部「労働生産性の国際比較」
» https://www.jpc-net.jp/intl_comparison/
なぜ、日本の労働生産性が低いのでしょうか?» https://www.jpc-net.jp/intl_comparison/
これについては様々な見方があるようですが、私は25年前に故ドラッカー博士が指摘した点を取り上げたいと思います。
1993年7月ダイヤモンド社刊「ポスト資本主義社会」(P.F.ドラッカー 著)の中で「日本語版への序文」が掲載されています。一部を引用します。
日本を今日のような経済大国に導いた経済と産業の力は、まさに工業化時代において行うべきことを、優れた規律と一貫性と卓越性のもとに行った結果、手にすることができたものである。
そして、まさにそのゆえに、新しい時代、すなわちポスト工業化の時代、ポスト社会主義の時代、ポスト資本主義の時代が要求するものは、日本に対して厳しいものとなる。成功を問題視することは、至難である。しかも、日本の成功はあまりに偉大である。
しかし今や、われわれは、極めて多くの分野において、すなわち事業活動、経済、企業組織、労働、情報、政治、政治体制、教育等の分野において、全く新たに考え直さなくてはならなくなっている。
これまでの成功をさらに磨き上げるのではなく、これからは、全く新しいことを行わなければならない。
それは心を躍らせる、刺激的かつ挑戦的な仕事である。しかし、辛い仕事である。
そして、まさにそのゆえに、新しい時代、すなわちポスト工業化の時代、ポスト社会主義の時代、ポスト資本主義の時代が要求するものは、日本に対して厳しいものとなる。成功を問題視することは、至難である。しかも、日本の成功はあまりに偉大である。
しかし今や、われわれは、極めて多くの分野において、すなわち事業活動、経済、企業組織、労働、情報、政治、政治体制、教育等の分野において、全く新たに考え直さなくてはならなくなっている。
これまでの成功をさらに磨き上げるのではなく、これからは、全く新しいことを行わなければならない。
それは心を躍らせる、刺激的かつ挑戦的な仕事である。しかし、辛い仕事である。
ドラッカー博士は、1960年代から日本に注目し、日本の成功から世界が学ぶように発信してきた学者の一人です。しかし、その成功は工業化時代においてのものであり、博士が唱える次の時代、ポスト資本主義社会での成功にはつながらないことをこの著書で訴えています。
では、ポスト資本主義社会とは何か、工業化時代とは何が違うのか、このことを明らかにする必要があります。
工業化時代の中心テーマは、モノづくりであり、その生産の進め方・やり方の最適化を求めることが課題でした。フレデリック・テイラーが唱えた「科学的管理法」が一つの答えとして、産業界で導入が進みました。その原理は「課業管理」、「作業の標準化」、「作業管理のために最適な組織形態」の3つからなります。
20世紀初頭に打ち出された概念ですが、第2次大戦後すべてを失った日本が奇跡の復興をなし遂げられたのは、製造業において科学的管理法に基づいて徹底した取り組みがなされた結果といえます。
製造業においては、この「課業管理」「作業の標準化」「作業管理のための最適な組織形態」の3つは現在も業務改善の重要なテーマです。
ドラッカー博士は、言います。
ポスト資本主義社会が直面することになる新しい課題は、知識労働者の生産性とサービス労働者の生産性にかかわる問題である。このうち、知識労働者の生産性の向上には、諸々の組織の構造とともに、社会構造そのものの抜本的な改革が不可欠となる。
40年前、知識労働者とサービス労働者は、就業人口の三分の一以下にすぎなかった。今日先進国では、彼らは、就業者人口の五分の四には足りないが、四分の三には達している。その割合は、さらに伸びつつある。
まさに今日では、物を作ったり運んだりする人たちの生産性ではなく、彼らの生産性が、先進国経済そのものの生産性を意味する。
(中略)
物を作ったり運んだりする労働においては、仕事は所与であり、その内容は一定である。フレデリック・W・テイラーは、砂をすくう仕事について分析したとき、砂をすくうこと自体は所与とした。しかも物を作ったり運んだりする仕事の多くは「機械」のペースで行われる。つまり、人間が機械に仕える。
しかし知識労働の仕事のすべて、およびサービス労働の仕事のほとんどにおいては、機械のほうが、仕事をする人間に仕える。仕事は所与ではない。決めていかなければならない。
かつての作業分析や「科学的管理法」では、「この仕事から期待すべきものは何か」という問いは発せられなかった。しかし、知識労働者やサービス労働者を生産的な存在とするためには、この問いを発することが不可欠である。
もちろんこの問いに答えるためには、リスクを伴う意思決定が必要である。しかも通常、選択肢は複数存在する。
したがって、得るべき成果を明確に特定しないかぎり、生産性の向上は望めない。
40年前、知識労働者とサービス労働者は、就業人口の三分の一以下にすぎなかった。今日先進国では、彼らは、就業者人口の五分の四には足りないが、四分の三には達している。その割合は、さらに伸びつつある。
まさに今日では、物を作ったり運んだりする人たちの生産性ではなく、彼らの生産性が、先進国経済そのものの生産性を意味する。
(中略)
物を作ったり運んだりする労働においては、仕事は所与であり、その内容は一定である。フレデリック・W・テイラーは、砂をすくう仕事について分析したとき、砂をすくうこと自体は所与とした。しかも物を作ったり運んだりする仕事の多くは「機械」のペースで行われる。つまり、人間が機械に仕える。
しかし知識労働の仕事のすべて、およびサービス労働の仕事のほとんどにおいては、機械のほうが、仕事をする人間に仕える。仕事は所与ではない。決めていかなければならない。
かつての作業分析や「科学的管理法」では、「この仕事から期待すべきものは何か」という問いは発せられなかった。しかし、知識労働者やサービス労働者を生産的な存在とするためには、この問いを発することが不可欠である。
もちろんこの問いに答えるためには、リスクを伴う意思決定が必要である。しかも通常、選択肢は複数存在する。
したがって、得るべき成果を明確に特定しないかぎり、生産性の向上は望めない。
「仕事は所与とは考えない」ゼロベースで「この仕事から期待すべきものは何か」を考え、意思決定すること、これが働き方改革を進める上で大変重要です。
日本電産の記事で日本電産コパルが取り組んでいる事例として、社員が定型・非定型それぞれどんな業務を持っているかを調べ、4つに仕分けしていることが紹介されています。つまり、(1)不要な業務(即座にやめる)、(2)複数の人が同じような業務をしている(統合する)、(3)一つの仕事を複数の人で分担(負荷の差を調べ平準化する)、(4)必要で問題ない(継続)の4つに仕分けして、業務改善に取り組まれています。
また、真の働き方改革とするため、1,000億円を投じるそうです。その中心課題として管理職の育成が挙がっています。
職場には、これまでの慣習で継続している仕事がたくさんあることでしょう。
「この仕事から期待するものは何か」。この問いから、働き方改革がはじまります。マネジメント層がしっかりとこの質問を発し、そして答え、様々な方策の中で最適策を意思決定するスキルが求められます。
コンセプチュアルスキルの向上が求められているように思います。
 この記事へのご意見・ご感想や、筆者へのメッセージをお寄せください(こちら ⇒ 送信フォーム)
この記事へのご意見・ご感想や、筆者へのメッセージをお寄せください(こちら ⇒ 送信フォーム)