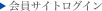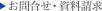人材育成コラム
“人財”育成のツボ
2018/1/22 (連載 第104回)
「自己マスタリー」が生産性向上の鍵を握る
ITスキル研究フォーラム 人財育成コンサルタント / PSマネジメントコンサルティング 代表
安藤 良治
今年はどんな年になるでしょう。みんなが幸せに過ごせる年になることを願っています。
1月9日の日経新聞で2018年はいろいろな意味で節目の年である、と紹介されていました。
世界金融危機から10年、日本の銀行危機のピークからも20年
平成の時代は30年目を迎え、明治維新からも150年に当たる。
明治初期に3500万人だった人口が、大正に5000万人、1967年に1億人を突破して、今世紀には1億2700万人に達した。
現在の日本の課題は「人口減少と高齢化」とされているが、70年前の日本では、人口が8千万人を超えた年に「人口過剰問題」が取り上げられ、当時は深刻な問題だった。
この記事では、「人口減少と高齢化が進むので、経済の停滞は避けられないという議論は、単なる言い訳にすぎない。重要なのは、人口が減っても高い経済成長を実現する生産性の上昇であり、それを可能にする経済改革である。」とまとめています。平成の時代は30年目を迎え、明治維新からも150年に当たる。
明治初期に3500万人だった人口が、大正に5000万人、1967年に1億人を突破して、今世紀には1億2700万人に達した。
現在の日本の課題は「人口減少と高齢化」とされているが、70年前の日本では、人口が8千万人を超えた年に「人口過剰問題」が取り上げられ、当時は深刻な問題だった。
(1月9日日経新聞朝刊 スタンフォード大 星教授による「経済教室」より)
人口増や人口減を理由とすることなく、しっかりと事業に向き合い、生産性を高める努力をすることが大事とする星教授の意見に賛同します。
ではどうやって「生産性を高めていくか」この課題にしっかり取り組んでいくことが2018年の課題といえましょう。
その答えは、「自己マスタリー」にあると考えます。
「自己マスタリー」は、これまでも何度か取り上げてきたピーター・センゲの「学習する組織」の5つのディシプリンの1つです。
第8章「自己マスタリー」より、2カ所抜粋して紹介したいと思います。
「自己マスタリー」は、個人の成長と学習のディシプリンを指す表現である。高度な自己マスタリーに達した人は、人生において自分が本当に求めている結果を生み出す能力を絶えず伸ばしていく。学習する組織の精神は、こうしたたゆまぬ学びの探求から生まれるのだ。(中略)
ここで述べている「学習」というのは、知識を増やすという意味ではなく、人生で本当に望んでいる結果を出す能力を伸ばすという意味だ。それは生涯つづく生成的学習である。学習する組織は、あらゆる階層でそれを実践する人がいなければ成り立たない。
ここで述べている「学習」というのは、知識を増やすという意味ではなく、人生で本当に望んでいる結果を出す能力を伸ばすという意味だ。それは生涯つづく生成的学習である。学習する組織は、あらゆる階層でそれを実践する人がいなければ成り立たない。
個人が学習することによってのみ組織は学習する。個人が学習したからといって必ずしも「学習する組織」になるとは限らない。が、個人の学習なくして組織の学習なし、である。
組織リーダーの中で、個人の学習に本気に取り組むためには企業哲学を根本的にあらためねばならないと認識する人は数えるほどしかいない。ファインセラミックス技術とエレクトロニクスの分野で世界をリードする京セラの創業者であり、社長、会長を経て1997年から名誉会長を務める稲盛和夫は、次のように語っている。
研究開発であれ、企業経営であれ、ビジネスは何事も「人」が原動力です。そして人には自分自身の意志があり、心があり、考え方があります。もしも社員に成長や技術開発の目標に挑む意欲が不足していれば……どんな成長も生産性の向上も技術開発もありはしないでしょう。
人の潜在能力を活用するには「潜在意識」「意志力」「心の動き……世の中の役に立ちたいという心からの願い」について新たな理解を得ることが必要になるだろう、と稲盛は考えている。京セラ社員に対しては、社是「敬天愛人」(天を敬い、人を愛す)に従って、「完璧」をめざしてたゆまず努力しながら、内面を見つめよと説いてきた。一方経営者としての自身の義務は、何よりもまず「社員に物心両面の幸福を与えること」だという。
学習する組織の中で何度も稲盛さんならびに京セラの哲学が紹介されています。それだけ稲盛哲学は、学習する組織に合致したものであるといえます。組織リーダーの中で、個人の学習に本気に取り組むためには企業哲学を根本的にあらためねばならないと認識する人は数えるほどしかいない。ファインセラミックス技術とエレクトロニクスの分野で世界をリードする京セラの創業者であり、社長、会長を経て1997年から名誉会長を務める稲盛和夫は、次のように語っている。
研究開発であれ、企業経営であれ、ビジネスは何事も「人」が原動力です。そして人には自分自身の意志があり、心があり、考え方があります。もしも社員に成長や技術開発の目標に挑む意欲が不足していれば……どんな成長も生産性の向上も技術開発もありはしないでしょう。
人の潜在能力を活用するには「潜在意識」「意志力」「心の動き……世の中の役に立ちたいという心からの願い」について新たな理解を得ることが必要になるだろう、と稲盛は考えている。京セラ社員に対しては、社是「敬天愛人」(天を敬い、人を愛す)に従って、「完璧」をめざしてたゆまず努力しながら、内面を見つめよと説いてきた。一方経営者としての自身の義務は、何よりもまず「社員に物心両面の幸福を与えること」だという。
確かに、組織は人で成り立っている、一人ひとりの人が「その気」になって取り組んでいなければ、経営者が望む成長も発展もありはしない、その通りです。
そこで、自己マスタリーを高めよと号令をかけたり、強引に研修プログラムなどを組んで受講させたりする組織が出てきます。しかし、自己マスタリーは個人の意識の問題ですから、誰も強制はできません。個人が自由な選択ができる中で組織が望む自己マスタリーをどうやって発揮してもらうか?
私は2012年7月のコラムで リコーの浜田元社長の著書「浜田広が語る『随所に主となる』を引用して、「新たなビジネスにはどんな人材が必要か」「それは随所に主となる人材である」との考えをお伝えしました。
浜田さんの著書の引用箇所を再掲載すると、
「お役立ち」と「納得」がリコーのキーワードだとすると、「随所に主となる」が経営者や管理職のための行動のキーセンテンスである。随所に主となるという状況をどれだけつくることができるかというのが、トップマネジメントや管理職にとって重要なのだ。(中略)現場にとって最適なことは、現場にいる部下が判断することなのだ。(中略)
「随所に主となる」というのは臨済宗の祖、臨済(867年没、唐の禅僧)の言葉からきたものだが、「随所に主となれ」という言い方をする人がいる。「主となれ」でも、「主となる」でも似たようなものと思うかもしれないが、まったく違う。「なれ」とオーダーするのではない。「なる」ように、どうやって仕組むかなのである。随所に主とならなければいけない。なってくれなければいけないのである。ならせるのではないのだ。さすがに禅の言葉である。
「随所に主となる」というのは臨済宗の祖、臨済(867年没、唐の禅僧)の言葉からきたものだが、「随所に主となれ」という言い方をする人がいる。「主となれ」でも、「主となる」でも似たようなものと思うかもしれないが、まったく違う。「なれ」とオーダーするのではない。「なる」ように、どうやって仕組むかなのである。随所に主とならなければいけない。なってくれなければいけないのである。ならせるのではないのだ。さすがに禅の言葉である。
主体的に取り組めと連呼したところで社員がその気になっていなければ、その連呼はむなしく空回りをするだけです。
どうやって、主体的に取り組んでもらうか、「主となる」ように仕向けるのが経営者であり、マネジメントの役割といえるでしょう。浜田さんは、この経営者の思いを著書で伝え、稲盛さんもまた「社員が主となるように」哲学を説いて、皆が自己マスタリーを高める努力をするようにされてきたのだと思います。
人は何かに取り組んでいると「もっとうまくなりたい」とか「もっと知りたい」といった自分を高めようとする心が自然と湧いてきます。その対象が、スポーツだったり、趣味の領域だったりすると明確に「もっと向上したい気持ち」が高まります。
「自分を高めたい気持ち」にスイッチを入れることは、特別なことではなく、ちょっとした「機会」があればできることだといえます。ただ、個人的な領域では、さめることも早く、壁の到来とともに「向上心」の持続が困難にもなります。
仕事において「自分を高めたい気持ち」にスイッチを入れ、持続的に自分を高める努力を続けること。これには、明確なビジョンやメンタル・モデルが必要になってきます。
そうです「学習する組織」の5つのディシプリン「自己マスタリー」「共有ビジョン」「メンタル・モデル」そして「チーム学習」と「システム思考」、これらは密接に絡み合い、それぞれが機能することで「学習する組織」となります。
株価は年初来3営業日で1,000円を上回り、荻野目洋子のダンシングヒーローがリバイバルと、まるでバブルが再来したかのように一部で盛り上がっている2018年の幕開けですが、真の幸せを求めて「自己マスタリー」を高めようではありませんか。